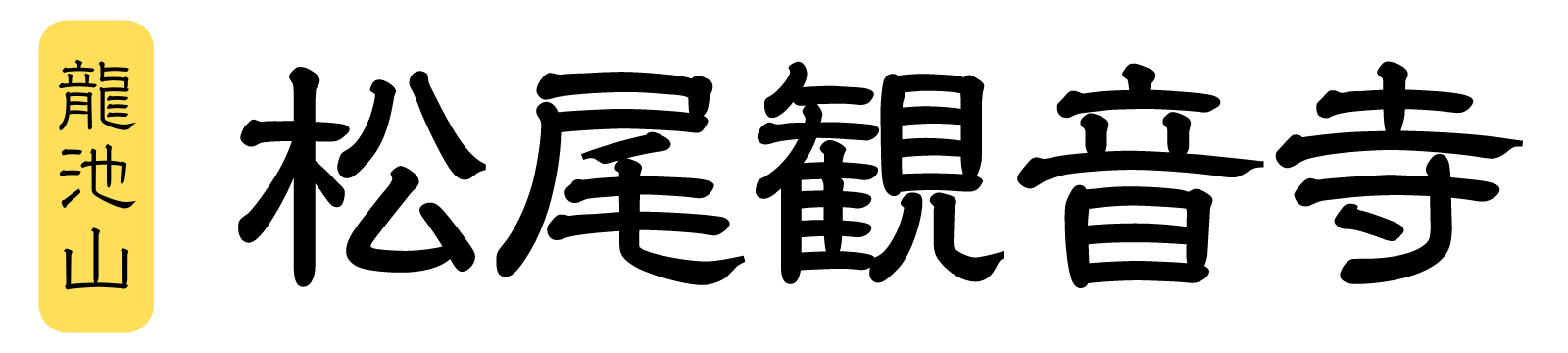一年の厄を払う日
初午の由来は全国各地さまざまな言い伝えがありますが、当地では古来から特に厄年に関係なく老若男女が毎年、一年の厄災を払う日として3月初の午(うま)の日に観音参り(松尾詣で)をするという風習があります。
この風習は、約1,300年前の当寺創建のきっかけとなった、厄災消除のご利益がある雄・雌2匹の双龍にまつわり、その後に起こった“龍神伝説”の時代から更に盛んになり、火災という大変な災難から無事逃れられた観音様と古来から言い伝えられる龍神様の「厄除開運」のご利益にあやかって、観音様にお参りすることで今年一年、災難から逃れることができ、さらに運が開け福が舞い込むと言われています。
また、この伊勢独自の珍しい風習が残っています。
- 厄落とし
-
ご祈祷を受けて授かったお札・お守りの代わりに、自分の身に付けている物を何か一つ(ハンカチが多いです)境内に落として行くことで一年の厄を落とす。
※現在新型コロナウイルス感染拡大防止の為、実施しておりません。
- 厄祝い
-
本厄を迎えると親戚・友人など多くの人に当寺の御影札に贈り物を付けて配り、自分の厄を少しづつ分けて持ってもらう。
- ねじりおこし
-
【ねじりおこし】と呼ばれる大棒状の岩おこしをねじった物を『厄をねじ切る』と言い縁起物として買う。
- 猿はじき
-
【猿はじき】と呼ばれる、装飾された竹の棒に付けられた猿ぼぼを竹のバネで上へはじく玩具を『厄をはじき去る』と言い、縁起物として買う。